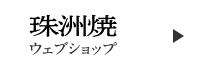技法
炭化焼成 たんかしょうせい







黒く丈夫なやきものを生み出す、古代の技法
〈技法〉
1週間に及ぶ窯焚きの最後、温度が最も高くなったのちに、窯の中に酸素を入りにくくして、不完全燃焼の状態で数時間焚き続けます。瓦などでも同様の焼成の最後に不完全燃焼の状態をつくり、表面を灰色にする方法は採られています。しかし、珠洲焼は長時間の炭化焼成によって、表面だけでなく土の内側まで濃い灰色から黒に変色していきます。
1200度までは、酸素がよく入るよう焚き口を開けて薪を入れていきます
 「炭化」に入ります。焼き上がったことを確認してから、焚き口を小さくします。薪を投じる時だけ、薪の投入口を開け、酸素を入りにくくしながら焚きます。窯の中は不完全燃焼のため、黒い煙が立ち上り続けます。季節や窯の状態にもよりますが、1〜3時間、この状態を続けます。
「炭化」に入ります。焼き上がったことを確認してから、焚き口を小さくします。薪を投じる時だけ、薪の投入口を開け、酸素を入りにくくしながら焚きます。窯の中は不完全燃焼のため、黒い煙が立ち上り続けます。季節や窯の状態にもよりますが、1〜3時間、この状態を続けます。
 最後に薪を大量に投入した上で、薪の投入を終えます。焚き口を煉瓦で、煙出し(煙突部)を金属板で閉じます。隙間から酸素が入らないようにするために、左官コテで泥(水を含めた土)を塗り埋めていきます。密閉した状態で窯を冷まし、4〜5日後に窯出しを行います。
最後に薪を大量に投入した上で、薪の投入を終えます。焚き口を煉瓦で、煙出し(煙突部)を金属板で閉じます。隙間から酸素が入らないようにするために、左官コテで泥(水を含めた土)を塗り埋めていきます。密閉した状態で窯を冷まし、4〜5日後に窯出しを行います。
珠洲焼の技法
叩き たたき






紐状になった土を積み上げて壺や甕をつくる際に、結合させ締めていくために、筋目の入った羽子板形の板で叩いていきます。珠洲焼の大きな特徴は、回転して横に叩いていくのではなく、縦に一列ずつ叩くことです。
このとき、一方向に連打すると、叩いた跡は右下りの平行線となり、また各列おきに右下り、左上りとなるよう道具をもち替えると、綾杉文になります。壺を割れにくくするために始まったものが、装飾も兼ねて発展した技法です。
叩きの跡は縦の列になっている
叩きに使う道具。外側から叩くためのもと、内側でそれを受けるための円形のものがある。斜線の切り込みは、表面に付いた際に、離れやすくする役割を持つが、文様として意識されるようになると、さまざまな彫り方が登場したと考えられている
珠洲焼の技法
櫛目 くしめ






櫛のように、複数の切れ目の入った木製や竹製のヘラを撫でながら、表面に複数の線が並行になって刻んでいきます。
波状や帯状など、自由に大きく描いたものが数多く残されています。
珠洲焼の技法
土づくり つちづくり